どうも。ムン太です。
北海道で警戒すべき寄生虫の感染症に、エキノコックス症があります。
僕はずっと田舎育ちなので、エキノコックスの感染予防のため学校の砂場が完全に使えなくなったり、公園の噴水で遊ぶなって言われたり、何かと嫌な、怖い思いをしています。
小さい頃、ずっとエキノコックスに怯えて、キツネも怖く、すごく神経質に暮らしていました。
エキノコックスはキツネの糞尿を媒介して人に感染する寄生虫で、感染の発覚が遅れれば死に至ることもあるので、川の水に触れたり、山菜を食べるときには特に注意が必要です。
北海道在住の方はもちろん、北海道旅行や移住などをお考えの方は、エキノコックスの自分でできる感染対策を知る必要があります。
北海道でキツネにあったときどうすべきか、自然の中でどうすべきか。
北海道に比べると数は少ないですが、北海道以外でもエキノコックスが確認されたりもしていますから、そもそも誰もが持っていて良い知識の一つだと思います。
エキノコックスの感染予防について、症状、感染率、そして北海道ではどんな駆除(駆虫)を行っているかなど、キツネとエキノコックスの関係を詳しくまとめます。
もくじ
エキノコックスの自分でできる感染対策

まず、一番大事なところなので、エキノコックスのご自分で行える感染対策をお伝えします。
北海道に訪れる機会、特に自然に触れる機会があるときにはとにかく実行してもらいたいことです。
エキノコックス感染対策に手洗いは絶対

エキノコックスの感染対策の基本中の基本(風邪の予防でもそうですね)、手洗いです。
外に出たら手を洗う、自然に触れたら手を洗うということは徹底しなければなりません。
沢水や川の水は絶対飲まない

ちょっとしたハイキングなどをしていると、川や沢水に触れることがあると思いますが、絶対に飲んではいけません。
近くでキツネが糞尿をしていれば、川の水にエキノコックスが紛れ込んでいる可能性があります。
山菜などはよく洗うか加熱する

山菜などを採る季節、食べ方には注意です。
生でかじることなんてないと思いますが、よく洗うか、加熱することが重要。
エキノコックスは熱に弱いので、加熱するのが確実です。
野性のキタキツネに触らない

野性のキタキツネにエキノコックスは寄生しているので、道で見かけても近寄ったり触ったりしないようにしましょう。
飼い犬の放し飼いをしない
飼い犬の放し飼いはしないようにしましょう。これは道内にお住まいの方へしてほしい感染予防です。
放し飼いにしている犬も、ネズミを口にしていたりすればエキノコックスに感染している可能性があります。
犬への感染は駆虫剤で完治しますから、感染の心配がある場合は動物病院に相談しましょう。
放し飼いの猫や野良猫にも注意
これまで、猫にエキノコックスは感染しにくい、しても猫の体内では成長しないと考えられていたのですが、2007年、猫の糞からエキノコックスが発見されたことから、猫を媒介しての感染もあり得るということが分かりました。
ネズミを捕食する野良猫や、外で放し飼いにする習慣のある猫には注意して、野良猫にも近寄らない、飼い猫も外に出るのなら検査を行うという処置を取ると良いでしょう。
エキノコックスの感染が心配な方は定期健診

エキノコックスは早期発見・治療することで治すことができますので、定期健診を受けると良いです。
感染を自分で確認することはできないので、定期的に血液検査をしてエキノコックスに感染していないかどうか確かめます。
早期発見・治療を行えば治療は可能ですが、末期状態になると治療は大変困難になります。
道内では市町村でスクリーニング検査をしていたり、お近くの保健所で検査を受け付けてもらえますので、問い合わせてみると良いでしょう。
道外にお住まいでエキノコックスの感染が心配な方の検査方法

北海道外の方のエキノコックスの検査方法もあります。
そういえばあのとき北海道に旅行で行って……という心当たりがあると心配ですよね。
以下のような機関に血清を郵送することで、検査を受けることができます。
北海道外の方は検査費が1,150円。
道内の方は760円となっています。
検査にあたって、採血を受ける病院との相談が必要になります
社団法人北海道臨床衛生検査技師会立衛生検査所
〒065-0019 札幌市東区北19条東17丁目
TEL 011-786-7072
以下の機関でも検査を受けることができます。
北海道立衛生研究所での検査は「検査のご案内」のページが詳しいです
早期発見すれば治療が可能な感染症なので、「あのとき北海道で……」と心配な方は検査を行っておくと安心ですよ(^^)
さて、エキノコックスの感染予防の知識を確実なものとするため、ここからは、キツネとエキノコックスに関する知識面のお話しもしておこうと思います。
キツネとエキノコックス感染の関係など

キツネとエキノコックスはしばしばセットで語られます。
これまで見てきたように、他の動物にもエキノコックスは感染するのですが、エキノコックスと言えばキツネというイメージが強いです。
キツネとエキノコックスの関係や、感染経路などについて簡単にまとめます。
エキノコックスは主にキツネとネズミに寄生

エキノコックスという寄生虫は、主にキツネとネズミに寄生して暮らしています。
エキノコックスは、ネズミの体内では卵がかえって幼虫になりますが、それ以上の成長はしません。
ヒトの身体でも同じように、幼虫から成長はしません。
幼虫を抱えたネズミを食べることでキツネに感染し、キツネの体内で成虫となり卵を産みます。
このように、宿主に合わせてエキノコックスは成長するのですが、ネズミのような卵を孵化させるために使う宿主を中間宿主、キツネのように成虫となって暮らすための宿主を終宿主と呼びます。
以下の動画で説明されているように、本来エキノコックスの一生はキツネとネズミの間の感染のさせ合いで成立しています。
このネズミとキツネのサイクルに、人間や、他の動物が入り込んでしまうことがあります。
エキノコックスの感染経路はキツネからヒト

エキノコックスの感染経路は、終宿主であるキツネや犬、そして猫などの終宿主となる動物の糞尿に触れ、口に入るというケースに限られます。
キツネはネズミを食べることでエキノコックスに感染しますが、ネズミは中間宿主なので、ネズミからヒトへの感染はしません。
エキノコックスは豚にも感染が認めたことがありますが、ブタからヒト、ヒトからヒトへの感染もしません。
エキノコックスが住み着く場所が腸内であれば、排せつ物からヒトの口に入る可能性がありますが、ネズミやブタ、そしてヒトには肝臓に住み着くので、感染の可能性がないのです。
北海道以外でエキノコックスの感染の危険はないの?
エキノコックスは基本的に全世界に広く分布する寄生虫ですが、日本国内では北海道で主に流行しています。
ただし、北海道以外で感染はありえないということはなく、全国で感染者が認められています。
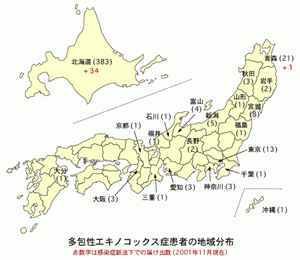
出典 Nlld国立感染症研究所
かつて北海道で生活したことがある方であるケースや、旅行などで犬と移動するケース、また発生源が不明なケースとあります。
国内では北海道が中心的な流行地ですが、移動の機会があればどこでも流行する可能性があります。
もっとも基本的な知識はこれくらいでしょうか。
続いて、エキノコックスにかかったらどんな症状が出るか、気になりますよね。
検査の前にこんな不調があるとか分かれば良いんだけど…とか、そもそも感染している確率ってどれくらいなの?という疑問に答えていきたいと思います。
エキノコックスの症状や感染率は?

エキノコックスの症状や感染率についてまとめます。
怖いのは、潜伏期間が長く、しばらく無症状のままエキノコックスの成長が続くってこと。
エキノコックスの症状は?

エキノコックスは潜伏期間が長く、症状が出るまでに数年から十数年かかるのが大きな特徴です。
子どもで5年~10年、成人では十数年から20年以上、なんの症状も出ないことがあります。
エキノコックスの感染に気付くことなく主に肝臓に住み着き、膨満感や黄疸、体力の低下などの症状が表れたときにはかなり重度の肝臓障害を来している状態です。
当然、放置すれば死に至ります。
また、エキノコックスは肺や脳に転移することもあります。
末期になり、エキノコックスが作る嚢胞が摘出できない状態になると治療は困難になります。
エキノコックスの感染率は?

エキノコックスの感染率を正確に知るのは難しいですが、北海道では毎年約10名~20名前後の方がエキノコックスにかかっています。
厚生労働省検疫所のエキノコックスに関するページによると、発症率は地域により異なりますが、「常在地域であれば10万人当たり50人以上」と言った確率になるそうです。
ただし、この10万人中50人というのは日本国内に限った話ではないので、あくまで参考の値です。
それにしても、数字が実感しにくいですね(^^;
最新がん統計によると、がんの罹患率が10万人あたり男性で約800人、女性で550人となっていますから、10万人あたり50人というのは決して大きくもないが、それほど小さい数字でもないと感じると思います。
エキノコックスが口に入ったからといって、確実に感染するということではありません。
過度に心配するものでもないけれど、無知は怖いというのがエキノコックス症です。
エキノコックスの感染リスクは高いの?低いの?

結局、エキノコックスの感染リスクは高いのでしょうか、低いのでしょうか。
エキノコックスの感染リスクを推し量るのは本当に難しいです。
北海道で川下りをした経験があるが、そのとき少し川の水を飲んでしまった。
絶えず流れる川の水を飲んだときの感染リスクは非常に低いです。ただし、絶対ありえないとも言えない。
以前道にいるキタキツネを触ってしまった。そういえばその後手を洗わずに食事をとってしまった。
毎年20名前後という罹患者の数と照らし合わせると、この程度で感染するとは考えにくいです。しかし、やはり絶対とは言えないですし、キツネに触れるのは止めるべきです。
国内で感染が絶対にないと言えるまでには、エキノコックスの根絶を目指す必要があります。
エキノコックスの感染率を減らすための研究や対処が行われていますので、ご紹介したいと思います。
北海道によるキツネ駆除(駆虫)の効果

エキノコックスの感染発見以来、北海道では様々な対策をとってきました。
北海道のエキノコックス対策経緯を簡単に!
「北海道のエキノコックス症対策―行政の取り組みについて―」という資料を参考に、これまで北海道が行ってきたエキノコックス対策を簡単にご説明します。
まず1970年以降、エキノコックス対策として、キツネの駆除が行われました。
駆除を進めてきましたが、結果的に感染の拡大が止まらないことから、駆除効果が疑問視されました。
キツネとの共存を計った上でエキノコックス対策を行っていくという方針が打ち出されたのは1987年。
そして2000年以降、ベイト(駆虫薬入りのエサ)の散布が検討され、現在まで実験的に散布効果を確かめながら、根絶を目指しています。
ただし、同資料によると、「2017年の時点で、ベイト散布を行っている地域は13市町村に限られる」と記述されており、道内全域の駆除は難しいという実態が窺えます。
キツネやネズミへの感染率を下げる対策

酪農学園大学におけるエキノコックスの感染リスク評価という研究の資料が見られます(PDFのダウンロードが必要です)。
このような研究の前例により、ベイトの散布によりキツネのエキノコックスの感染は一時0%にまで抑えられたが、散布を止めると40%程度にまで戻っていたというような結果が検証されてきました。
ベイトの効果的な利用のため、散布場所や長期の散布といった方法が検証され、課題となります。
現状はこの酪農学園大学のように、小規模な、スケールを限定しての駆虫と、結果の検証が繰り返されているのが現状です。
道全域の駆虫となると、効果の面はもちろん、コストの面から考えてもこのような研究が必要なのですが、エキノコックスの完全な駆虫が完了するまでは、私たち個人が感染予防をしていく必要がありますね。
キツネとエキノコックス対策!感染予防の知識と症状!感染率や駆除について まとめ

北海道での対策にもまだ課題があり、エキノコックスの完全な根絶は達成できていない状況です。
北海道にお住まいの方はもちろん、旅行などで北海道を訪れる方は、自分で行えるエキノコックスの感染予防や対策をしっかり行うことが大切!
エキノコックスの感染は過度に心配する必要はありませんが、例えばお子さんなどは自衛的に感染予防を行うのは難しいでしょうから、私たち大人が要所をよく押さえておく必要があります。
そしてもし不安があるなら、積極的に検査を行うことも重要です。
エキノコックス症は早期発見と早期治療により治療効果が高まる感染症ですから予防することが第一ですが、速やかな検査というのも重要なポイントです。



コメントを残す